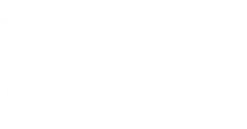ホームページのSEO対策を自分で実践したいと考えている方は多いのではないでしょうか。
専門業者に依頼すると高額な費用がかかるため、できれば自社で対策を進めたいというのが本音でしょう。
本記事では、ホームページのSEO対策を自分で実践する具体的な方法を、初心者にもわかりやすく解説します。
効率的な集客施策として、すぐに取り組める基本的な対策から、中長期的に効果を発揮する施策まで、実践的なノウハウをお伝えします。
自分でSEO対策を実践する5つのステップ
ホームページのSEO対策を自分で実践するには、まずタイトルとメタディスクリプションを設定し、週1〜2回のペースでブログ記事を書き、月1回効果測定をするというサイクルを回すことです。
SEO対策と聞くと専門的で難しいイメージがありますが、実は基本的な施策は誰でも実践できます。専門業者に依頼すると月額5万円〜30万円程度かかることもありますが、自分で行えばその費用を大幅に抑えながら成果を出すことが可能です。
具体的な実践ステップは以下の通りです。第一に、各ページのタイトルタグとメタディスクリプションを設定します。これは1日あれば完了する作業で、最も基本的ながら効果的な施策です。第二に、キーワードを選定してブログ記事を作成し始めます。週1〜2回、2000文字以上の記事を書くことを目標にしましょう。
第三に、Googleサーチコンソールとアナリティクスに登録し、サイトマップを送信します。これにより、検索エンジンにページを認識してもらえます。第四に、画像を圧縮してページ速度を改善し、モバイル対応を確認します。第五に、月1回アクセス解析を確認し、どのページが見られているか、どのキーワードで流入しているかをチェックして改善します。
10年以上Web制作に携わってきた経験から言えば、この5つのステップを3ヶ月間継続すれば、確実に効果が現れ始めます。重要なのは、完璧を目指さず、できることから始めて継続することです。
自分でSEO対策を実践することで、費用を抑えながら自社のビジネスに最適化された施策を展開できます。
では、これらのステップで使用する具体的なツールについて見ていきましょう。
SEO対策に必要な無料ツール
ホームページのSEO対策を自分で実践する際、いくつかの無料ツールを活用することで効率が大幅に向上します。
Googleサーチコンソール
最も重要なツールがGoogleサーチコンソールです。これは、Googleが無料で提供している、サイトの検索パフォーマンスを分析するツールです。どのキーワードで検索されているか、検索順位はどれくらいか、クリック率はどうかなどが一目でわかります。
また、サイトに技術的な問題がある場合も通知してくれます。インデックスされていないページや、モバイルでの表示に問題があるページなどを発見できるため、早期に対処できます。サイトマップを送信する機能もあり、新しいページを素早くGoogleに認識してもらえます。
Google Analytics
訪問者の行動を詳しく分析できるツールです。どのページがよく見られているか、どこから訪問しているか、滞在時間はどれくらいかなどが把握できます。
特に重要なのは、直帰率と平均セッション時間です。直帰率が高いページは、コンテンツに問題がある可能性があります。逆に、滞在時間が長いページは、ユーザーに価値を提供できている証拠です。これらのデータを基に、改善すべきページを特定できます。
キーワードプランナー
Google広告のツールですが、無料でキーワードの検索ボリュームを調べられます。どのキーワードがどれくらい検索されているかを知ることで、効果的なコンテンツ作成が可能になります。
ただし、詳細な検索ボリュームを見るには広告を出稿する必要があります。無料版でも大まかな範囲(100〜1000、1000〜1万など)は確認できるため、十分参考になります。
PageSpeed Insights
ページの表示速度を測定し、改善点を提案してくれるツールです。モバイルとデスクトップの両方で測定でき、具体的な改善項目が数値とともに表示されます。
画像の最適化、JavaScriptの遅延読み込み、キャッシュの活用など、技術的な提案もしてくれます。全てを理解できなくても、画像サイズの削減など、簡単に実践できる項目から取り組めます。
ラッコキーワード
関連キーワードを調べる無料ツールです。メインキーワードを入力すると、それに関連する検索キーワードが一覧で表示されます。ブログ記事のテーマを考える際に非常に便利です。
これらのツールを組み合わせることで、専門業者に頼らずとも効果的なSEO対策が可能になります。
次に、コンテンツ作成における具体的なテクニックを見ていきましょう。
検索上位を狙うコンテンツ作成テクニック
ホームページのSEO対策を自分で実践する上で、質の高いコンテンツ作成は最も重要な要素です。
タイトルの付け方
記事タイトルには、必ず狙うキーワードを含めます。ただし、キーワードを詰め込むのではなく、自然な文章にすることが重要です。例えば「渋谷 美容院 おすすめ」というキーワードなら、「渋谷でおすすめの美容院10選|失敗しない選び方」のように作ります。
数字を入れることで具体性が増し、クリック率が向上します。また、「失敗しない」「完全ガイド」「徹底解説」などの言葉を加えることで、読者の興味を引けます。文字数は30〜35文字以内に収めましょう。
見出し構成の作り方
記事を書く前に、見出し構成を作ることが重要です。h2、h3タグを使って論理的な構造を作ります。検索結果の上位ページを参考に、どのような内容が求められているかを把握しましょう。
見出しだけで記事の内容がわかるようにすることがポイントです。また、各見出しには自然な形でキーワードやその関連語を含めます。ただし、全ての見出しにキーワードを入れる必要はありません。
冒頭文の重要性
記事の冒頭200〜300文字は特に重要です。ここで読者の疑問に対する答えを簡潔に示すことで、「この記事には求めている情報がある」と理解してもらえます。
冒頭文では、検索キーワードを2〜3回自然に含めつつ、記事で何がわかるのかを明確に伝えます。また、結論を先に述べることで、読者の離脱を防げます。
専門性と独自性の出し方
他のサイトと同じような内容では上位表示は困難です。自社の経験や専門知識を活かした情報を盛り込みましょう。実際のお客様の事例、業界の最新動向への見解、失敗から学んだ教訓など、あなただからこそ書ける内容を含めることが重要です。
具体的な数字やデータを示すことも効果的です。「多くの人が」ではなく「当社調査では70%の人が」のように表現することで、説得力が増します。
適切な文章量と読みやすさ
一般的に、2000〜5000文字程度のコンテンツが望ましいとされています。ただし、文字数だけが目的になってはいけません。読者の疑問に対して十分な回答を提供することを優先しましょう。
また、読みやすさも重要です。1段落は3〜4行程度に抑え、適度に改行を入れます。箇条書きや表を使って、情報を整理することも効果的です。漢字とひらがなのバランスにも注意し、専門用語は必要に応じて説明を加えます。
画像や図解の活用
テキストだけでなく、適切な画像や図解を入れることで、理解度が高まります。また、画像のalt属性にキーワードを含めることで、画像検索からの流入も期待できます。
ただし、画像は必ず圧縮してからアップロードしましょう。大きな画像ファイルは、ページ速度を低下させ、SEOに悪影響を及ぼします。
これらのテクニックを実践することで、検索上位を狙える質の高いコンテンツが作成できます。
では、技術的な設定についても確認しておきましょう。
必ず行うべき技術的な設定
ホームページのSEO対策を自分で実践する際、技術的な基本設定も重要です。
タイトルタグとメタディスクリプション
各ページに固有のタイトルタグとメタディスクリプションを設定します。WordPressなら、Yoast SEOやAll in One SEOなどのプラグインで簡単に設定できます。
タイトルタグには、そのページで狙うキーワードを含め、30〜35文字以内にまとめます。メタディスクリプションは120文字程度で、ページの内容を魅力的に説明します。これらは検索結果に表示されるため、クリック率に直結します。
見出しタグの階層構造
h1タグはページに1つだけ使用し、ページの主題を表します。通常、記事タイトルがh1になります。h2、h3タグは階層的に使用し、コンテンツの論理的な構造を作ります。
h2の中にh3を配置し、h3の中にh4を配置するという階層を守ることが重要です。h2の次にいきなりh4を使うような飛ばし方は避けましょう。
URL構造の最適化
URLは短く、内容がわかりやすいものにします。日本語URLは避け、英数字で構成します。例えば、ブログ記事なら「https://example.com/blog/seo-howto/」のように、意味のあるURLにしましょう。
WordPressの場合、パーマリンク設定で「投稿名」を選択し、記事ごとにカスタムURLを設定できます。
XMLサイトマップの送信
XMLサイトマップは、サイトの全ページをリスト化したファイルです。これをGoogleサーチコンソールから送信することで、新しいページを素早くインデックスしてもらえます。
WordPressなら、SEOプラグインで自動生成されます。生成されたサイトマップのURLをGoogleサーチコンソールに登録するだけで完了です。
SSL化(HTTPS対応)
SSL証明書を導入し、URLをHTTPSにすることは必須です。多くのレンタルサーバーでは、無料のSSL証明書を提供しています。サーバーの管理画面から簡単に設定できることが多いです。
SSL化後は、全てのページがHTTPSでアクセスできるよう、リダイレクト設定を行います。また、Googleサーチコンソールには、HTTPSのURLでプロパティを追加しましょう。
ページ速度の改善
ページの読み込み速度は、SEOに直接影響します。PageSpeed Insightsで測定し、スコアが低い場合は改善に取り組みましょう。
最も効果的なのは画像の圧縮です。TinyPNGなどのツールで画像を圧縮してからアップロードします。また、不要なプラグインを削除したり、キャッシュプラグインを導入したりすることも有効です。
これらの技術的な設定を行うことで、検索エンジンがホームページを正しく理解し、適切に評価できる基盤が整います。
次に、自分でSEO対策をする際によくある失敗パターンとその対策を見ていきましょう。
自分でSEO対策をする際の失敗例と対策
ホームページのSEO対策を自分で実践する際、多くの人が陥りがちな失敗があります。
キーワードを詰め込みすぎる
SEO対策を意識しすぎて、キーワードを不自然に詰め込むのは逆効果です。「渋谷 美容院」というキーワードで対策したいからと、「渋谷の美容院は渋谷駅近くの美容院として渋谷で人気の美容院です」のように、不自然にキーワードを繰り返すのは避けましょう。
現在の検索エンジンは、文脈を理解できます。自然な文章の中に適切な頻度でキーワードを含めることが重要です。文章全体の3〜5%程度を目安に、読者にとって違和感のない範囲で使用しましょう。
コピーコンテンツを作成する
他のサイトの内容をそのままコピーしたり、少し言い回しを変えただけの記事を作ったりするのは、Googleからペナルティを受ける可能性があります。検索順位が大きく下がったり、インデックスから削除されたりすることもあります。
必ず自分の言葉で、オリジナルの情報を提供しましょう。参考にしたサイトがあっても、自社の視点や経験を加えて、独自のコンテンツに仕上げることが重要です。
更新を継続できない
最初は意気込んで週2〜3回更新していても、1ヶ月で途切れてしまうケースがよくあります。SEO対策は継続が命です。3ヶ月、6ヶ月と続けることで、徐々に効果が現れます。
無理のないペースを設定することが重要です。週1回が難しければ、2週間に1回でも構いません。完璧な記事を目指すより、定期的に情報を発信し続けることを優先しましょう。
効果測定をしない
アクセス解析を見ずに、ただ記事を書き続けるのは非効率です。どのページがよく見られているか、どのキーワードで流入しているかを把握することで、効果的な施策が見えてきます。
月に1回は必ずGoogleサーチコンソールとアナリティクスを確認し、データに基づいて改善を進めましょう。感覚ではなく、数字で判断することが重要です。
被リンクを無理に獲得しようとする
被リンク(他のサイトからのリンク)はSEOに重要ですが、質の低いサイトからのリンクは逆効果です。リンク販売サイトから購入したり、相互リンク目的のサイトに大量登録したりするのは避けましょう。
自然な形で被リンクを獲得するには、質の高いコンテンツを作ることが最も確実です。SNSで共有したり、業界のメディアに寄稿したりすることで、徐々に被リンクが増えていきます。
これらの失敗を避けることで、効率的にSEO対策を進められます。
では、SEO対策に関して外注すべき施策と自分で行うべき施策の見極め方について考えてみましょう。
外注すべき施策と自分で行うべき施策
ホームページのSEO対策を自分で実践する際、全てを自分で行う必要はありません。適切に外注することで、より効率的に成果を出せます。
自分で行うべき施策
コンテンツ作成は、できるだけ自分で行うべきです。自社のサービスや商品について最も詳しいのは、他でもない自分自身です。外部のライターに依頼しても、専門性や独自性のある記事を書いてもらうのは困難です。
また、基本的なタグ設定(タイトル、メタディスクリプション、見出し)も自分で行えます。これらはWordPressのプラグインやCMSの管理画面から簡単に設定できるため、外注する必要はありません。
アクセス解析の確認と改善方針の決定も、自分で行うべきです。数字を見て、どこに問題があるか、どう改善すべきかを判断するのは、ビジネスオーナー自身が最も適しています。
外注を検討すべき施策
技術的に高度な施策は、専門家に依頼することを検討しましょう。例えば、サイトの構造を大幅に変更する、JavaScriptを最適化する、構造化データを実装するなどは、専門知識が必要です。
誤った設定をすると、サイトが表示されなくなったり、検索順位が大きく下がったりするリスクがあります。こうした施策は、SEO専門会社やエンジニアに依頼する方が安全です。
また、被リンク獲得のための営業活動も、外注を検討する価値があります。業界メディアへの寄稿依頼や、関連サイトとの提携交渉などは、専門業者のネットワークを活用する方が効率的な場合があります。
費用対効果で判断する
外注するかどうかは、費用対効果で判断しましょう。例えば、月額3万円で専門家に技術的な最適化を依頼し、その結果月10件の問い合わせが増えるなら、十分に投資価値があります。
一方、月額10万円かけてコンテンツ作成を外注しても、自社の専門性が伝わらない記事しか上がってこないなら、自分で書いた方が良いでしょう。
段階的に外注を増やす
最初は全て自分で行い、効果が出始めたら外注を増やすというアプローチがおすすめです。基本的な施策を自分で実践し、SEOの仕組みを理解した上で、専門家に依頼する方が、適切な判断ができます。
また、自分で行った施策の効果を測定し、どこにボトルネックがあるかを把握してから外注先を選ぶことで、無駄な費用を抑えられます。
適切に外注を活用しながら、自分でできることは自分で行うというバランスが、最も効率的なSEO対策につながります。
最後に、長期的に成果を出し続けるためのポイントを確認しておきましょう。
長期的にSEO効果を維持する方法
ホームページのSEO対策を自分で実践し、長期的に成果を出し続けるためのポイントを紹介します。
コンテンツの定期的な見直し
一度作成したコンテンツも、定期的に見直して更新することが重要です。情報が古くなっていないか、新しい知見を追加できないかをチェックしましょう。Googleは、最新の情報を提供しているサイトを高く評価します。
特に、アクセスの多いページは優先的に更新します。3ヶ月〜6ヶ月に1回は内容を見直し、必要に応じて情報を追加したり、表現を改善したりしましょう。更新日時が新しくなることで、検索順位にもプラスの影響があります。
ユーザーの行動データを活用
Google Analyticsで、ユーザーがどのページをよく見ているか、どこで離脱しているかを分析します。滞在時間が短いページは、コンテンツに問題がある可能性があります。
また、検索クエリのデータから、ユーザーがどんな情報を求めているかを把握できます。意外なキーワードで流入がある場合、そのテーマで新しい記事を作成することで、さらなる集客が期待できます。
競合サイトの動向を監視
自社サイトだけでなく、競合サイトの動きにも注目しましょう。新しいコンテンツを公開していないか、デザインをリニューアルしていないか、どんなキーワードで上位表示されているかなどを定期的にチェックします。
競合が力を入れているキーワードは、そこに需要がある証拠です。同じキーワードでより質の高いコンテンツを作ることで、競合から流入を奪えます。
最新のSEOトレンドを学ぶ
検索エンジンのアルゴリズムは定期的に更新されます。GoogleのSEO関連の公式ブログや、信頼できるSEO情報サイトをチェックし、最新のトレンドを把握しましょう。
ただし、小手先のテクニックに飛びつくのではなく、「ユーザーにとって価値のあるコンテンツを提供する」という基本方針を守ることが重要です。この原則に沿っていれば、アルゴリズム変動の影響は最小限に抑えられます。
PDCAサイクルを回す
SEO対策は、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)のサイクルを継続的に回すことが成功の鍵です。月に1回は必ず効果を測定し、うまくいった施策は継続し、効果が薄い施策は見直すという改善を繰り返しましょう。
記録を残すことも重要です。いつ、どんな施策を行ったか、その結果どうなったかをメモしておくことで、自社に最適なSEO戦略が見えてきます。
チーム体制を作る
可能であれば、社内でSEO対策のチームを作りましょう。一人で全てを担当するより、コンテンツ作成担当、効果測定担当、技術対応担当のように役割分担することで、継続しやすくなります。
また、定期的にミーティングを行い、成果や課題を共有することで、モチベーションも維持できます。
ホームページのSEO対策を自分で実践することで、費用を抑えながら着実に成果を上げることができます。
基本的なタグ設定から始め、質の高いコンテンツを継続的に作成し、データに基づいて改善を繰り返すことが、長期的な成功への道です。焦らず、一つ一つの施策を丁寧に実行し、3ヶ月、6ヶ月と継続することで、検索からの集客を確実に増やしていきましょう。専門業者に全てを任せるのではなく、自分で基本を押さえることで、本当に効果的なSEO対策が実現できます。