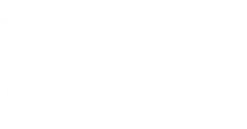せっかくホームページを作ったのに、更新できない状態が続いていませんか?
「時間がない」「何を書けばいいか分からない」と感じる経営者は少なくありません。
実は、こうした悩みには、いくつかの典型的なパターンと解決策があります。
放置したままでは、せっかくの集客チャンスを逃してしまいます。
この記事では、10年以上web制作に携わってきた経験から、ホームページが更新できない原因と解決方法について詳しく解説していきます。
ホームページが更新できない理由と解決策
ホームページが更新できない理由は、主に5つのパターンに分類でき、それぞれに効果的な解決策があります。
多くの経営者が「更新しなければ」と思いながらも実行できずにいます。日々の業務に追われて時間が取れない、何を書けばいいかネタが思いつかない、操作が難しくて自信がない、更新の重要性を実感できない、担当者が決まっていないなど、理由は様々です。
実際、約7割の企業が「月1回も更新できていない」という調査結果もあります。しかし、原因を特定し適切な対策を取れば、更新できない状態は必ず改善できます。
具体的には以下の5つです。
- 時間がなくて更新できない:日々の業務に追われ後回しになる
- 更新ネタが思いつかない:何を書けばいいか分からず止まる
- 操作方法が難しい:技術的なハードルで諦めてしまう
- 更新の重要性を感じない:効果が見えず優先度が低い
- 担当者が不明確:誰が更新するか決まっていない
このように、更新できない原因を明確にすれば、適切な対策で解決できます。
ではまずは、時間がなくて更新できない場合について詳しく見ていきたいと思います。
日々の業務で時間が取れず更新できない場合の対策
ホームページが更新できない最も多い理由は、日々の業務に追われて時間が取れないことです。
経営者や担当者は、顧客対応、営業活動、事務作業など、やるべきことが山積みです。その中で「ホームページの更新」は緊急性が低いため、どうしても後回しになってしまいます。「今日は忙しいから明日やろう」「来週まとめて更新しよう」と先延ばしにしているうちに、気づけば半年、1年と経ってしまうのです。
特に中小企業では専任のWeb担当者を置く余裕がなく、他の業務と兼任しているケースが多いため、この傾向は顕著です。また、更新作業自体に慣れていないと、1つの記事を書くのに数時間かかってしまい、ますます時間が取れなくなる悪循環に陥ります。
解決策としては、まず更新作業を「ルーティン化」することが効果的です。例えば、毎週月曜日の午前中30分だけと決めて、必ずその時間に更新作業を行います。カレンダーに予定として組み込み、他の予定を入れないようにすることで、確実に時間を確保できます。
また、スマートフォンから更新できる環境を整えれば、移動時間や待ち時間などの隙間時間を活用できます。さらに、更新作業を細分化することも重要です。「記事を書く」という大きなタスクではなく、「写真を撮る(5分)」「タイトルを考える(5分)」「本文を書く(15分)」「投稿する(5分)」のように分解すれば、短時間でも進められます。
完璧を求めすぎず、100点の記事を月1回よりも、60点の記事を週1回の方が効果的だと割り切ることも大切です。どうしても時間が取れない場合は、月額制のサポートサービスを利用して更新を代行してもらう選択肢もあります。
時間がなくて更新できない場合は、ルーティン化と作業の細分化で解決できます。
次に、更新ネタが思いつかないという問題について解説します。
何を書けばいいか分からず更新できない場合のネタ探し
ホームページが更新できない理由として、何を書けばいいか分からないというケースも非常に多いです。
「自社のことを書くネタなんてない」「業界のことは皆知っているから書く意味がない」「特別な出来事がないから更新することがない」と感じている経営者は少なくありません。しかし実際には、日々の業務の中に更新ネタは溢れています。ただ、それが「ネタになる」と気づいていないだけなのです。
特に専門的な知識や経験が豊富な経営者ほど、「こんな当たり前のこと」と思い込んで情報発信を避ける傾向があります。しかし、顧客から見ればその「当たり前」こそが価値ある情報なのです。また、ネタを探そうとする時に「特別なこと」「大きなニュース」を書かなければと考えすぎて、ハードルを上げてしまうこともあります。
解決策としては、まず「ネタ帳」を作ることをおすすめします。日々の業務の中で「これは説明したほうがいいな」「よく聞かれる質問だな」「お客様が喜んでくれた」と感じたことをメモしていきます。
例えば、顧客からの質問はそのまま記事のネタになります。「どのくらいの期間がかかりますか?」という質問が多ければ、「〇〇サービスの一般的な流れと期間について」という記事が書けます。また、施工事例やビフォーアフター、季節ごとの注意点、業界の豆知識、スタッフ紹介、仕入れ先の紹介、地域の話題など、切り口を変えれば無限にネタは見つかります。
さらに、競合他社のサイトを参考にすることも有効です。他社が書いている内容を自社の視点で書き直せば、オリジナルコンテンツになります。「〇〇の選び方」「よくある失敗例」「費用相場について」など、定番のテーマも効果的です。一度書いたネタも、数ヶ月後に情報を更新して再投稿できるため、ネタ切れの心配は実はほとんどありません。
更新ネタが思いつかない場合は、日々の業務の中から顧客目線でネタを見つける習慣をつければ解決できます。
続いて、操作方法が難しいという問題について見ていきましょう。
操作が難しくて更新できない場合の簡単な方法
ホームページが更新できない理由として、操作方法が難しくて手が出せないというケースがあります。
「HTMLやCSSなんて分からない」「管理画面が複雑で何をどうすればいいか分からない」「間違って大事なところを消してしまいそうで怖い」という不安から、更新作業を避けてしまう人は多いです。特に、制作会社に依頼して作ってもらったサイトを引き継いだ場合、操作説明を受けても時間が経つと忘れてしまい、結局更新できなくなります。
また、WordPressのような高機能なCMSは、できることが多い反面、初心者には複雑に感じられます。プラグインやテーマの設定、エディタの使い方、画像の挿入方法など、覚えることが多すぎて挫折してしまうのです。さらに、「下手に触ってサイトを壊してしまったらどうしよう」という恐怖心が、更新をためらわせる大きな要因になっています。
解決策としては、まず「簡単に更新できるシステム」を選ぶことが重要です。WordPressでもブロックエディタ(Gutenberg)を使えば、文章と画像を配置するだけで記事が作れます。まずは「投稿」機能だけを使い、お知らせやブログを更新することから始めましょう。固定ページやデザインのカスタマイズは触らず、記事の追加だけに絞ればリスクは最小限です。
また、事前にテストページや下書き機能を使って練習することで、操作に慣れることができます。間違えても「公開」ボタンを押さなければサイトに反映されないため、安心して試せます。さらに、スマートフォンアプリから更新できるCMSも増えているため、パソコンが苦手な人でも直感的に操作できる環境を整えられます。
どうしても難しい場合は、専門的な部分は制作会社に任せ、簡単な文章更新だけを自社で行うという分業も効果的です。月額制のサポート付きサービスなら、分からないことをすぐに質問でき、代行も依頼できるため、技術的なハードルを下げられます。
操作が難しくて更新できない場合は、簡単な機能から始め、徐々に慣れていけば解決できます。
次は、更新の重要性を感じないという問題について説明します。
更新の効果が見えず優先度が低くなる場合の意識改革
ホームページが更新できない理由として、更新の重要性や効果を実感できず、優先度が低くなっているケースがあります。
「更新してもアクセスが増えた実感がない」「問い合わせにつながっているか分からない」「他にやるべきことが多すぎる」という状況では、更新作業は後回しになります。特に、目に見える効果がすぐに表れないため、「やってもやらなくても同じ」と感じてしまうのです。
営業活動なら「今日何件訪問した」「何件受注した」と成果が明確ですが、ホームページ更新は「検索順位がじわじわ上がる」「信頼性が少しずつ高まる」という長期的な効果のため、実感しにくいのです。また、経営者自身がインターネットで情報収集をしない世代の場合、「ホームページなんて誰も見ていない」と思い込んでいることもあります。
解決策としては、まず更新の効果を「見える化」することが重要です。Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールを導入し、「今月は何人訪問があった」「どの記事がよく読まれている」「どのページから問い合わせがあった」を数値で確認します。数字で見ると、確実に効果が出ていることが分かり、モチベーションが上がります。
また、問い合わせフォームに「どこで当社を知りましたか?」という質問項目を追加し、「ホームページ経由」の割合を把握することも効果的です。実際、新規顧客の3〜5割はホームページ経由というデータも珍しくありません。
さらに、競合他社のサイトと比較してみることで、危機感を持つこともできます。競合が毎週更新しているのに自社は放置している状況を見れば、更新の必要性を実感できるでしょう。経営層向けに月次レポートを作成し、「今月の更新回数」「アクセス数の推移」「問い合わせ件数」を報告することで、組織全体の意識も高まります。
更新の重要性を感じない場合は、効果を数値化して見える化することで優先度を上げられます。
最後に、担当者が不明確な場合の体制づくりについて解説します。
担当者が決まっておらず更新できない場合の体制構築
ホームページが更新できない理由として、誰が更新するのか担当者が明確でないケースがあります。
「誰かがやるだろう」「時間がある人がやればいい」という曖昧な状態では、結局誰も更新しません。特に中小企業では、Web担当という専任ポジションを作れないため、総務、営業、経営者本人など、複数人が「なんとなく関わっている」状態になりがちです。その結果、「自分の仕事ではない」という意識が生まれ、誰も責任を持たなくなります。
また、担当者を決めても、その人が退職したり部署異動したりすると、引き継ぎが不十分で更新が止まってしまうこともあります。さらに、権限の問題もあります。更新内容を上司に確認してから公開するルールになっていると、承認待ちで時間がかかり、更新頻度が下がります。
解決策としては、まず「更新責任者」を明確に決めることです。できれば1人に絞り、その人の業務として位置づけます。ただし、1人だけに任せるのではなく、サポート体制も整えます。例えば、営業部からネタを提供してもらう、経営者が最終確認をする、外部のサポートサービスを利用するなど、チームで更新する仕組みを作ります。
また、更新マニュアルを作成し、誰でも更新できる状態にしておくことも重要です。担当者が不在でも他の人が代わりに更新できれば、継続性が保たれます。さらに、更新ルールを明文化することで、スムーズな運用が可能になります。「毎週金曜日に1記事投稿」「承認は48時間以内」「季節の挨拶は総務が担当」など、具体的に決めることで、誰が何をするか明確になります。
定期的に担当者会議を開き、更新状況の共有や改善点の討議を行うことで、組織全体のWeb活用意識も高まります。
担当者が不明確な場合は、責任者を決めてチーム体制を構築することで継続的な更新が可能になります。