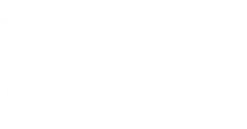ホームページを公開したら、それで終わりではありません。
その後にやるべき重要な設定や作業があることをご存知ですか? 実は、初期設定を怠ると、せっかくのホームページも効果が半減してしまいます。
検索エンジンに認識されない、アクセス解析ができない、セキュリティが甘いなど、問題は様々です。
この記事では、10年以上web制作に携わってきた経験から、公開後にやることについて詳しく解説していきます。
ホームページ公開後にやるべき5つのこと
ホームページ公開後には、効果を最大化するために5つの重要な作業があります。
多くの方が、ホームページを公開した時点で安心してしまいます。しかし実際には、公開はスタート地点に過ぎず、そこから適切な設定を行わなければ、期待した効果は得られません。検索エンジンへの登録、アクセス解析の設定、セキュリティ対策、SNS連携、定期更新の計画など、公開後すぐに取り組むべきことは多岐にわたります。これらを適切に行うことで、サイトの効果は数倍にも高まります。
具体的には以下の5つです。
- 検索エンジンへの登録:GoogleやBingに存在を認識してもらう
- アクセス解析の設定:訪問者の行動を把握し改善に活かす
- セキュリティ対策の実施:サイトを守り安全性を確保する
- SNSとの連携:情報拡散の仕組みを作る
- 更新計画の策定:継続的な運用体制を整える
このように、公開後にやるべきことを実行すれば、ホームページの効果を最大化できます。
ではまずは検索エンジンへの登録について詳しく見ていきたいと思います。
検索エンジンへの登録で存在を知らせる
ホームページ公開後、最初にやるべきことは、検索エンジンへの登録です。
公開しただけでは、GoogleやBingなどの検索エンジンは、あなたのサイトの存在を知りません。自動的にクロール(巡回)されて登録されるのを待つこともできますが、数週間から数ヶ月かかることもあります。その間、どんなにキーワードで検索しても、あなたのサイトは表示されず、新規顧客を獲得できません。そこで、自ら検索エンジンに「新しいサイトを作りました」と申請する必要があるのです。
Google Search Consoleへの登録
最も重要なのは、Google Search Console(グーグルサーチコンソール)への登録です。Googleのアカウントがあれば無料で利用でき、サイトのURLを登録することで、Googleにサイトの存在を知らせられます。
登録手順は以下の通りです。まず、Google Search Consoleにアクセスし、Googleアカウントでログインします。次に、「プロパティを追加」をクリックし、サイトのURLを入力します。所有権の確認方法はいくつかありますが、HTMLファイルをアップロードする方法が一般的です。指示に従ってファイルをダウンロードし、サーバーにアップロードすれば、数分で確認が完了します。
登録後は、「サイトマップ」を送信することも重要です。サイトマップとは、サイト内の全ページのURLをリスト化したファイルで、これを送信することでGoogleが効率的にページをクロールできます。WordPressなら、「Yoast SEO」などのプラグインで自動生成できます。
Bing Webmaster Toolsへの登録
Google Search Consoleと並んで重要なのが、Bing Webmaster Tools(ビングウェブマスターツール)への登録です。日本ではGoogleのシェアが圧倒的ですが、Bingも一定数のユーザーがいます。特に、企業のパソコンではMicrosoft Edgeが標準ブラウザとして使われることが多く、Bingでの検索も無視できません。
登録方法はGoogle Search Consoleと似ており、Microsoftアカウントでログインし、サイトURLを登録、所有権を確認するだけです。さらに、Google Search Consoleのデータをインポートできる機能もあるため、二度手間を省けます。
検索エンジンへの登録は、公開後すぐに行うことで、早期に検索結果に表示されるようになります。
次に、アクセス解析の設定について解説します。
アクセス解析ツールで訪問者の動きを把握する
ホームページ公開後にやるべき重要なことの2つ目は、アクセス解析ツールの設定です。
アクセス解析を導入しなければ、「何人が訪れたのか」「どのページが人気なのか」「どこから来たのか」「何分滞在したのか」といった重要なデータが一切分かりません。これでは、サイトが効果を上げているのか、改善が必要なのか、判断のしようがありません。アクセス解析は、サイト運営の羅針盤であり、必ず導入すべきツールです。
Google Analytics 4の設定
最も広く使われているのが、Google Analytics 4(GA4)です。無料で高機能なツールで、訪問者数、ページビュー、滞在時間、離脱率、コンバージョン率など、あらゆるデータを詳細に分析できます。
設定手順は以下の通りです。まず、Google Analyticsのサイトにアクセスし、Googleアカウントでログインします。「測定を開始」をクリックし、アカウント名とプロパティ名を設定します。次に、データストリームを作成し、ウェブサイトのURLを入力します。すると、測定IDが発行されるので、このIDをサイトに設置します。
WordPressなら、「Site Kit by Google」などのプラグインを使えば、コードを触らずに簡単に設置できます。HTMLサイトの場合は、発行されたトラッキングコードを、全ページの<head>タグ内に貼り付けます。設置後、数時間でデータが表示され始めますが、正確な分析には1〜2週間のデータ蓄積が必要です。
Google Tag Managerの活用
より高度な計測を行いたい場合は、Google Tag Manager(GTM)の導入もおすすめです。GTMを使えば、コンバージョン計測、イベント追跡、外部リンクのクリック計測など、詳細な分析が可能になります。特に、問い合わせフォームの送信完了を計測することで、「どのページから問い合わせがあったか」を把握でき、効果的なページを特定できます。
また、アクセス解析では以下のポイントに注目しましょう。ユーザー数とセッション数で人気度を測り、ページ別の滞在時間で満足度を確認し、離脱率の高いページを改善し、流入元を分析して効果的な施策を強化します。月次レポートを作成し、数値の変化を追うことで、サイトの成長を実感でき、改善のヒントも得られます。
アクセス解析ツールを設定することで、データに基づいた戦略的なサイト運営が可能になります。
続いて、セキュリティ対策の実施について見ていきましょう。
セキュリティ対策でサイトを守る
ホームページ公開後にやるべき3つ目のことは、セキュリティ対策の実施です。
公開したばかりのサイトは、セキュリティ設定が不十分なことが多く、ハッカーの標的になりやすい状態です。特に、初期設定のままのIDやパスワード、古いバージョンのCMS、不要なプラグインなどは、脆弱性を抱えています。公開直後にしっかりとセキュリティ対策を行うことで、将来的なリスクを大幅に減らせます。
SSL証明書の導入(HTTPS化)
最も基本的で重要なのが、SSL証明書の導入です。SSLとは、通信を暗号化する技術で、これがないとブラウザに「保護されていない通信」と警告が表示され、訪問者に不安を与えます。また、GoogleはHTTPSをランキング要素としているため、SEOの観点からも必須です。
多くのレンタルサーバーでは、無料のSSL証明書(Let’s Encrypt)が提供されており、管理画面から数クリックで設定できます。設定後は、サイト内の全リンクをHTTPSに変更し、HTTPでアクセスされた場合は自動的にHTTPSにリダイレクトする設定も行います。WordPressなら、「Really Simple SSL」などのプラグインで一括設定が可能です。
管理画面のセキュリティ強化
次に重要なのが、管理画面へのログインセキュリティです。初期設定のユーザー名「admin」は変更し、パスワードは英数字記号を組み合わせた複雑なものにします。さらに、二段階認証を導入することで、たとえパスワードが漏れても不正ログインを防げます。
また、ログイン試行回数の制限も有効です。何度もパスワードを間違えると一定時間ログインできなくする設定で、総当たり攻撃を防げます。WordPressなら「Limit Login Attempts Reloaded」などのプラグインで簡単に設定できます。
定期的なバックアップ体制
万が一の事態に備えて、バックアップ体制を整えることも重要です。サイトのデータとデータベースを定期的にバックアップし、別の場所に保存します。WordPressなら「UpdraftPlus」などのプラグインで、自動バックアップを設定できます。週1回の自動バックアップを設定し、Google DriveやDropboxに保存すれば、サーバーがダウンしても復旧できます。
セキュリティ対策を公開直後に実施することで、安全なサイト運営の基盤を作れます。
次は、SNSとの連携について説明します。
SNSと連携して情報拡散の仕組みを作る
ホームページ公開後にやるべき4つ目のことは、SNSとの連携です。
サイト単体では、訪問者は検索エンジン経由か、直接URLを入力した人だけです。しかしSNSと連携することで、情報の拡散力が飛躍的に高まります。記事をシェアしてもらえれば、その友人・フォロワーにも届き、認知度が一気に広がります。また、SNSからの流入は、検索エンジンとは異なる層にアプローチでき、顧客の幅を広げられます。
シェアボタンの設置
最も基本的なのが、各ページにSNSシェアボタンを設置することです。Facebook、X(旧Twitter)、LINE、はてなブックマークなど、主要なSNSのシェアボタンを配置することで、訪問者が簡単に情報をシェアできます。特に、記事の最初と最後の両方に設置すると、シェア率が高まります。
WordPressなら「AddToAny Share Buttons」などのプラグインで簡単に設置できます。HTMLサイトの場合は、各SNSの公式シェアボタン生成ツールを使ってコードを取得し、サイトに埋め込みます。
OGP設定で魅力的に表示
SNSでシェアされた時に、魅力的に表示されるよう、OGP(Open Graph Protocol)の設定も重要です。OGPとは、SNSでシェアされた時に表示されるタイトル、説明文、画像を指定する技術です。適切に設定しないと、意図しない画像が表示されたり、タイトルが切れたりして、クリック率が下がります。
WordPressなら「Yoast SEO」などのプラグインでOGP設定ができます。各記事に、SNS用のタイトル(60文字以内)、説明文(120文字以内)、アイキャッチ画像(1200×630px推奨)を設定します。これにより、SNSでシェアされた時に、プロフェッショナルな見た目で表示され、クリック率が向上します。
公式SNSアカウントとの連動
企業の公式SNSアカウントを持っている場合は、サイトと連動させましょう。サイトのヘッダーやフッターにSNSアイコンを配置し、公式アカウントへのリンクを設置します。逆に、SNSのプロフィール欄にサイトURLを記載することで、相互に流入を促せます。
また、サイトに新しい記事を投稿したら、SNSでも告知します。「新しい記事を公開しました」と投稿し、記事へのリンクを貼ることで、フォロワーをサイトに誘導できます。定期的に更新情報を流すことで、「このアカウントは有益な情報を発信している」という認識が広がり、フォロワーも増えていきます。
SNSとの連携により、サイトの認知度と訪問者数を大幅に増やせます。
最後に、更新計画の策定について解説します。
継続的な更新計画を立てて運用体制を整える
ホームページ公開後にやるべき5つ目のことは、更新計画の策定と運用体制の構築です。
サイトは公開がゴールではなく、スタート地点です。公開後、定期的に更新し、情報を新鮮に保たなければ、検索順位は下がり、訪問者は減り、効果は失われます。そのため、公開直後に「いつ、誰が、何を、どのように」更新するかを明確にし、継続的な運用体制を整えることが重要です。
更新担当者の決定
まず、更新担当者を明確に決めます。「誰かがやるだろう」では、結局誰もやらず、サイトは放置されます。1人の責任者を決め、その人の業務として位置づけることで、継続性が保たれます。ただし、1人に全て任せるのではなく、サポート体制も整えます。営業部からネタを提供してもらう、経理部が料金情報を更新する、経営者が最終確認をするなど、チームで運用する仕組みを作ります。
更新スケジュールの策定
次に、更新スケジュールを決めます。「週1回、月曜日の午前中に1記事投稿」「月末に前月の実績を更新」など、具体的に決めることで、習慣化しやすくなります。カレンダーに予定として登録し、リマインダーを設定すれば、忘れることもありません。
また、年間計画も立てておくと効果的です。1月は新年の挨拶、2〜3月は確定申告関連、4月は新年度の挨拶、など、季節やイベントに合わせた記事を計画的に作成できます。
コンテンツカレンダーの作成
さらに進んで、コンテンツカレンダーを作成することもおすすめです。エクセルやGoogleスプレッドシートで、「日付」「担当者」「テーマ」「ステータス」などを管理します。これにより、誰が何をいつまでにやるかが明確になり、チーム全体で進捗を共有できます。
効果測定と改善のサイクル
更新するだけでなく、効果測定と改善も計画に組み込みます。月末にアクセス解析を確認し、「どの記事が人気だったか」「問い合わせは増えたか」「滞在時間は伸びたか」を分析します。人気記事の傾向を把握し、次回の記事に活かすことで、徐々にコンテンツの質が向上します。
また、四半期ごとにサイト全体を見直し、古い情報を更新し、リンク切れを修正し、デザインを改善します。PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を回すことで、サイトは常に最適な状態を保てます。
継続的な更新計画を立て、運用体制を整えることで、ホームページは長期的に効果を発揮し続けます。