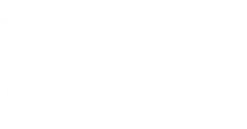「うちの会社にはホームページはいらないのでは?」と考えている経営者の方も少なくありません。
制作費用や維持費を考えると、本当に必要なのか疑問に思うこともあるでしょう。
確かに、すべてのビジネスに絶対的にホームページが必要というわけではありません。
しかし、現代のビジネス環境において、ホームページがいらないと判断するには慎重な検討が必要です。
この記事では、10年以上web制作に携わってきた経験から、ホームページが本当に不要なケースと、その判断基準について詳しく解説していきます。
ホームページの必要性は事業形態と顧客層で判断する
ホームページがいらないかどうかは、あなたの事業形態と顧客層によって判断すべきです。
多くの場合、ホームページは集客や信頼構築に不可欠なツールですが、特定の条件下では優先度が低くなることもあります。重要なのは、「ホームページがなくても事業が成立するか」「顧客がホームページを求めているか」という2点を冷静に分析することです。インターネットで情報を探さない顧客層をターゲットにしている場合や、完全紹介制のビジネスモデルであれば、ホームページの必要性は相対的に低くなります。
一方で、新規顧客の獲得を目指す場合や、若い世代をターゲットにする場合は、ホームページは必須に近い存在です。また、BtoBビジネスでは取引先がホームページで信頼性を確認するため、ないと商談すら難しくなります。
ビジネスの特性を理解した上で、ホームページの必要性を判断することが重要です。
次に、具体的にどのようなケースでホームページがいらないのかを見ていきましょう。
完全紹介制ビジネスではホームページの優先度が低い
完全に紹介だけで顧客を獲得しているビジネスでは、ホームページがいらない場合があります。
既存顧客からの口コミや紹介だけで十分な仕事が確保できており、新規顧客を積極的に探していない場合、ホームページへの投資効果は限定的です。例えば、高級会員制サロンや一部の専門コンサルタントなど、クローズドなビジネスモデルを採用している場合がこれに該当します。紹介者が直接説明してくれるため、ホームページで情報提供する必要性が薄いのです。
ただし、紹介されたお客様がサービス内容を確認したいと思った時、ホームページがないと不安を感じる可能性もあります。また、将来的に事業を拡大したい場合は、早めにホームページを用意しておく方が賢明です。
完全紹介制で顧客を獲得できているなら、ホームページの優先度は低いと言えます。
続いて、地域密着型の特定業種について解説します。
地域の常連客のみで成立する店舗ビジネス
地域の常連客だけで経営が成り立っている小規模店舗では、ホームページがいらない場合もあります。
近隣住民が徒歩や自転車で来店し、何年も通い続けてくれる常連客が売上の大半を占めているなら、新規顧客獲得のためのホームページは不要かもしれません。特に昔ながらの商店街の八百屋さんや、地域に根付いた理容室などは、ホームページなしでも十分経営できているケースが多いです。高齢者が主な顧客層で、インターネットをほとんど使わない場合は、チラシや口コミの方が効果的です。
しかし、後継者が事業を引き継ぐ際や、客層の高齢化で売上が減少してきた場合は、若い世代を取り込むためにホームページが必要になります。また、Googleマップでの表示や営業時間の案内など、最低限の情報発信は今や必須になりつつあります。
地域の常連客だけで成り立っているなら、ホームページがいらない場合もあります。
次は、SNSだけで十分なケースについて説明します。
SNSだけで集客できている一部のビジネス
InstagramやX(旧Twitter)などのSNSだけで十分な集客ができている場合、ホームページの優先度は下がります。
美容室やカフェ、ハンドメイド作家など、ビジュアルが重要な業種では、SNSの方が顧客とのコミュニケーションが取りやすく、集客効果も高いことがあります。特に若い世代をターゲットにしている場合、ホームページよりもInstagramのプロフィールを見て来店を決める人が多いのも事実です。投稿へのコメントやDMで気軽にやり取りでき、リアルタイムな情報発信も簡単です。
ただし、SNSは運営会社の方針変更やアルゴリズム変更の影響を受けやすく、アカウント停止のリスクもあります。また、検索エンジンからの流入を得られないため、「地域名+業種」で検索する顧客を取りこぼす可能性があります。
SNSだけで十分な集客ができているなら、ホームページは後回しにできます。
続いて、オフライン営業のみのBtoBについて見ていきます。
オフライン営業のみで完結するBtoBビジネス
訪問営業や展示会だけで顧客を獲得しているBtoBビジネスでは、ホームページがいらないと感じるかもしれません。
営業担当者が直接企業を訪問し、対面で商談を進めるスタイルが確立している場合、ホームページがなくても受注できることはあります。特に、特定の業界内で長年の実績があり、ネットワークが構築されている企業では、口コミや紹介だけで十分な場合もあります。パンフレットや提案書を直接渡せるため、ホームページで情報提供する必要性を感じないこともあるでしょう。
しかし実際には、商談前に取引先候補がホームページで会社の信頼性を確認するのが一般的です。ホームページがないと「本当に実在する会社なのか」と疑われ、商談機会を失うリスクがあります。また、若い世代の担当者は必ずネットで検索するため、ホームページがないことが不利に働きます。
オフライン営業だけで完結しているなら、ホームページは不要と感じるかもしれません。
次に、一時的・季節的なビジネスについて解説します。
短期間だけ運営する一時的なビジネス
期間限定のイベントや季節商品だけを扱う一時的なビジネスでは、ホームページ制作のコストが見合わない場合があります。
数ヶ月だけ営業する期間限定ショップや、年に一度のイベント販売などでは、ホームページを作成してもその後使わなくなる可能性が高いです。制作費用と維持費を考えると、SNSや無料ブログ、Googleマップへの登録だけで済ませた方が効率的かもしれません。特に初期投資を抑えたいスタートアップや、テスト的に始める事業では、まずは低コストで始めることが賢明です。
ただし、毎年同じイベントを開催する場合や、将来的に通年営業に移行する計画があるなら、早めにホームページを作っておく方が長期的にはメリットがあります。また、一時的でも多くの顧客を集めたいなら、簡易的でもホームページがあった方が信頼性は高まります。
短期間だけ運営するビジネスなら、ホームページのコストが見合わないこともあります。
最後に、ホームページが必要になるタイミングについて説明します。
ホームページが必要になる明確な判断基準
最終的に、以下のような状況になったら、ホームページがいらないという判断を見直すべきです。
新規顧客を増やしたい、売上を拡大したい、若い世代を取り込みたいと思った時は、ホームページが必須になります。また、競合他社がホームページを持っていて顧客を奪われている場合や、「ホームページはないんですか?」と聞かれることが増えた場合も、作成を検討すべきタイミングです。さらに、採用活動を強化したい、企業の信頼性を高めたい、オンラインでの情報発信を強化したいと感じたら、もはやホームページは選択肢ではなく必要な投資です。
逆に、現状のビジネスモデルで十分な利益が出ており、拡大の必要性を感じていないなら、無理にホームページを作る必要はありません。ただし、ビジネス環境は常に変化するため、定期的に必要性を再評価することをおすすめします。
上記のような状況になったら、ホームページがいらないという判断を見直すべきです。