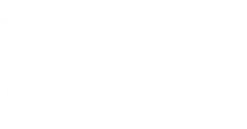訪問者にとって使いにくいサイトは、すぐに閉じられてしまいます。
せっかく良いサービスを提供していても、分かりやすい構成でなければ伝わりません。
実際、約6割の人が「欲しい情報がすぐ見つからない」という理由で離脱しています。
分かりやすいホームページを作ることは、売上に直結する重要なポイントです。
この記事では、10年以上web制作に携わってきた経験から、訪問者が迷わないホームページの設計原則について詳しく解説していきます。
分かりやすいホームページとは?
分かりやすいホームページとは、5つの原則を守って作られた訪問者が迷わないサイトのことです。
訪問者が求めているのは、シンプルで直感的に使える設計です。複雑なナビゲーション、分かりにくい構成、読みにくいデザインなどは、すぐに離脱の原因となります。実際、ユーザーは平均して3秒以内にサイトの使いやすさを判断すると言われており、第一印象で「分かりにくい」と感じれば二度と訪れません。逆に、分かりやすいサイトは滞在時間が長く、コンバージョン率も2倍以上高くなるというデータもあります。
具体的には以下の5つです。
- 明確な情報の階層構造:重要な情報ほど上位に配置し見つけやすくする
- 直感的なナビゲーション:迷わず目的のページにたどり着ける導線
- 読みやすい文章とレイアウト:ストレスなく情報を読み取れる工夫
- 視覚的な分かりやすさ:色や画像で情報を整理し理解を助ける
- レスポンシブデザイン:どの端末でも快適に閲覧できる設計
このように、これらの原則を守ることで分かりやすいサイトが作れます。
ではまずは、明確な情報の階層構造について詳しく見ていきたいと思います。
重要な情報を上位に配置する階層構造の設計
分かりやすいホームページには、重要な情報を上位に配置した明確な階層構造が必要です。
訪問者は、自分が求める情報を素早く見つけたいと思っています。そのため、サイト全体の情報を優先順位に基づいて整理し、重要度の高い情報ほど目立つ位置に配置することが重要です。例えば、トップページでは、企業の強みやサービスの特徴を最上部に置き、スクロールせずに見える範囲(ファーストビュー)で伝えるべき情報を完結させます。詳細情報は下層ページに配置し、興味を持った人が深掘りできる構造にするのです。具体的には、ファーストビューで「何の会社か」「何を提供しているか」「どんな強みがあるか」の3点を明確に示すことが重要です。
また、情報の階層は3クリック以内ですべてのページにアクセスできる深さが理想とされています。トップページから目的のページまでのクリック数が多すぎると、途中で諦めて離脱してしまいます。「会社概要」「サービス内容」「料金表」「お問い合わせ」など、よくアクセスされるページは必ず第2階層(トップページから1クリック)に配置します。さらに、パンくずリストを設置することで、訪問者が今サイトのどこにいるのかを常に把握でき、迷子になることを防げます。情報設計の段階で、ユーザーの行動を想定したサイトマップを作成し、どのページからどのページへ移動するのが自然かを考えることが、分かりやすいサイト作りの第一歩です。
重要な情報を上位に配置した階層構造が、分かりやすいホームページには必要です。
次に、直感的なナビゲーションの設計について解説します。
迷わず目的地に到達できるナビゲーションの設計
分かりやすいホームページには、訪問者が迷わず目的地に到達できる直感的なナビゲーションが不可欠です。
ナビゲーションは、サイトの道路標識のようなものです。どこに何があるのか、どうすれば目的のページにたどり着けるのかを明確に示す必要があります。グローバルナビゲーション(サイト全体で共通のメニュー)は、画面上部に固定し、すべてのページから主要なコンテンツにアクセスできるようにします。メニュー項目は5〜7個程度に絞り、それぞれ一目で内容が分かる名称にすることが重要です。例えば、「ソリューション」よりも「サービス内容」、「コンタクト」よりも「お問い合わせ」といった、日本語で分かりやすい表現を使います。横文字を使うとおしゃれに見えますが、訪問者を混乱させる原因になります。
また、ドロップダウンメニューを使う場合は、階層を深くしすぎないよう注意が必要です。2階層までに留め、それ以上深い情報は別のナビゲーション方法を検討します。さらに、重要な行動(問い合わせ、資料請求、購入など)に導くCTA(Call To Action)ボタンは、目立つ色とサイズで配置し、各ページに設置します。「お問い合わせはこちら」「今すぐ相談する」「無料で資料請求」など、具体的な行動を促す文言を使うことで、訪問者の次のアクションを明確にします。スマートフォンでは、ハンバーガーメニュー(三本線のアイコン)の使用が一般的ですが、重要なメニューは常に表示しておくなど、端末ごとの最適化も必要です。検索機能を設置することも、特にページ数が多いサイトでは有効な手段となります。
迷わず目的地に到達できるナビゲーションが、分かりやすいホームページには不可欠です。
続いて、読みやすい文章とレイアウトの工夫について見ていきましょう。
ストレスなく情報を読み取れる文章設計
分かりやすいホームページには、訪問者がストレスなく情報を読み取れる文章とレイアウトの工夫が必要です。
Webで読まれる文章は、紙の本とは異なる特性があります。訪問者は流し読みをすることが多く、重要な情報だけを素早く拾い読みします。そのため、1つの段落は3〜4行程度に抑え、長文は避けます。また、見出しを効果的に使い、内容を一目で把握できるようにします。見出しだけを読んでもページ全体の概要が分かる構成が理想です。文字サイズは16px以上を基本とし、行間(line-height)は1.5〜1.8倍程度に設定すると読みやすくなります。小さい文字は特に高齢者や視力の弱い人にとって大きなストレスとなるため、可読性を優先します。
さらに、箇条書きや番号付きリストを活用することで、情報を整理して伝えられます。例えば、サービスの特徴を説明する際、文章で書き連ねるよりも「・24時間対応」「・無料相談可能」「・即日対応」のように箇条書きにした方が、一目で理解できます。また、重要なキーワードや数字は太字にして強調し、視線を誘導します。ただし、強調しすぎると逆に読みにくくなるため、1段落に1〜2箇所程度に留めます。余白(ホワイトスペース)も重要で、文字や要素を詰め込みすぎず、適度な余白を取ることで視覚的な疲労を軽減できます。カラムレイアウトを使う場合も、1行の文字数は35〜50文字程度が読みやすいとされており、これより長いと読むのに疲れてしまいます。
ストレスなく情報を読み取れる文章設計が、分かりやすいホームページには必要です。
次は、視覚的な分かりやすさを高める工夫について説明します。
色と画像で情報を整理する視覚デザイン
分かりやすいホームページには、色と画像を効果的に使って情報を整理する視覚デザインが重要です。
人間は情報の約8割を視覚から得ていると言われており、色や画像の使い方がサイトの分かりやすさを大きく左右します。配色は基本的に、ベースカラー(背景色)70%、メインカラー(企業カラー)25%、アクセントカラー(強調色)5%の割合が理想です。色を使いすぎると情報が整理されず、逆に分かりにくくなります。特に、重要なボタンやリンクには一貫したアクセントカラーを使い、「この色をクリックすれば何かアクションができる」という学習効果を生みます。例えば、問い合わせボタンをすべて同じオレンジ色にすることで、訪問者は無意識にその色を探すようになります。
また、画像は単なる装飾ではなく、情報を伝える手段として活用します。サービスの流れを図解する、Before/Afterを写真で示す、複雑な仕組みをイラストで説明するなど、テキストだけでは分かりにくい情報を視覚化します。ただし、画像を多用しすぎるとページの読み込みが遅くなるため、適切に圧縮し、必要な場所にだけ配置することが大切です。さらに、アイコンを効果的に使うことで、情報を直感的に理解させられます。電話のアイコンは連絡先、カートのアイコンは購入、虫眼鏡のアイコンは検索など、一般的に認知されているアイコンを使用します。色のコントラストにも注意が必要で、特にテキストと背景のコントラスト比は4.5:1以上を確保し、視認性を高めることがアクセシビリティの観点からも重要です。
色と画像で情報を整理する視覚デザインが、分かりやすいホームページには重要です。
最後に、レスポンシブデザインの重要性について解説します。
あらゆる端末で快適に閲覧できる設計
分かりやすいホームページには、スマートフォンやタブレットなど、あらゆる端末で快適に閲覧できるレスポンシブデザインが必須です。
現代では、サイトへのアクセスの約7割がスマートフォンからと言われています。パソコン用に作られたサイトをスマートフォンで見ると、文字が小さすぎて読めない、ボタンが押しにくい、横スクロールが必要など、多くの問題が発生します。レスポンシブデザインとは、画面サイズに応じて自動的にレイアウトが最適化される設計手法で、1つのサイトで全ての端末に対応できます。スマートフォンでは、メニューをハンバーガーアイコンに格納し、コンテンツを縦一列に配置することで、スクロールだけで全ての情報にアクセスできるようにします。パソコンでは横に並べていた要素も、スマホでは縦に積み重ねることで見やすくなります。
また、タッチ操作を前提とした設計も重要です。ボタンやリンクのタップ領域は最低でも44×44px以上を確保し、誤タップを防ぎます。指で押しにくい小さなボタンは大きなストレスとなります。電話番号はタップで発信できるようにリンク化し、住所はタップで地図アプリが開くようにするなど、モバイルならではの利便性も考慮します。フォーム入力も、スマートフォンでは特に注意が必要で、項目を最小限に絞り、入力しやすいインターフェースを設計します。例えば、電話番号の入力欄では自動的にテンキーが表示されるようにする、日付選択はカレンダー形式にするなど、細かな配慮が使いやすさを大きく向上させます。Googleもモバイルフレンドリーなサイトを検索結果で優遇するため、SEO対策の観点からもレスポンシブデザインは必須です。
あらゆる端末で快適に閲覧できる設計が、分かりやすいホームページには必須です。